スティーブン・スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』。
冒頭数十分に及ぶおぞましい映像から気づくことがある。それは、「凄惨な映像を見せるのは良くないことだ」というような風紀委員っぽいことではない。おおよそ多くの人は、おどろおどろしいものを観ることで、何が正しいのかを「感じる」ことができるという人の可能性と素晴らしい側面。この逆説こそ気がつくべきことで、それを実際に教えてくれるのがこの映画だ。
ちょっと話が横道にそれるけれど『プライベート・ライアン』を観ていない、観たくない人のために他の例を用いると、麻薬を使っているシーン、男女の(愛というのではなく、欲の交換としての商業的な営みとしての)セックスシーン、少年兵ややせ細った途上国の子どもたちの映像、「好ましくない」映像は数多くあって、それらを観せられたときにも、僕たちは自分たちに内在している美しさと正しさを「感じられる」。
いうまでもなく、出稿前にも何度も修正のプロセスがあるし、本が出来上がっても、再度自分の本を読み直す。本質的な自問なのだけれど、「結局何がしたかったんだっけ」なんて振り出しに戻る感覚を味わう瞬間がある。未だプロセスの途中だし、それが終わることもないのだろうけれど、その自問の回答は今回の本で見えてきた。
「不自由を定義することで、自由が少し輪郭を帯びる。制限を明示することで、制限を受けないところを確保できる」という欲求と衝動。このひどく個人的なモチベーションが出発点でもある。そうして出来上がった本は、文字として出来上がれば僕の元を離れる。音楽や映画がそうであるように、現実に目を向ければ、本の一字一句、解釈、感想も、この本に関わるすべてのことがらは、すべて読み手のものだ。
スーツのルールや制限を読むことで生まれてくる、自分はこれが「正しい」と感じられる感覚。人間らしくて、自分らしくて、理由がなくても「好きだ」と言える。それが、一人ひとりにとっての真の正解で、誰にも決められない自分らしさであり個性。
控えめに言ってもこの類の本は、大きなお世話に違いないし、そもそも服のことについてあれこれ意見するのは無粋(もしくはダンディな姿勢からは真逆)なことの一つでもある(ブランメルは著書など残していない)。
「スーツはこうしろ」なんていう本を書いているけれど、語弊を恐れずに言えばスーツも所詮、外見でしかない。それを着た「人」を外見だけですべて理解するなんて誰だってできやしない。でも、恵まれた時代、恵まれた国に生まれたのだ。着るものを選ぶ自由がある。狭い自由かもしれない。ただ、その自由を楽しむ日々は、ありふれた幸せの一つで、世界の誰しもが得られるわけではない。そんな幸せがほんの少し増えたらいいなと、それがひどく当たり前だけれど、書き終えて残った感覚。
手にとってもらえたこと、ご購入、そして読んでいただいたこと。そうして、これも読んでもらえていること。末筆ではありますが、お礼を心より申し上げます。ありがとうございました。

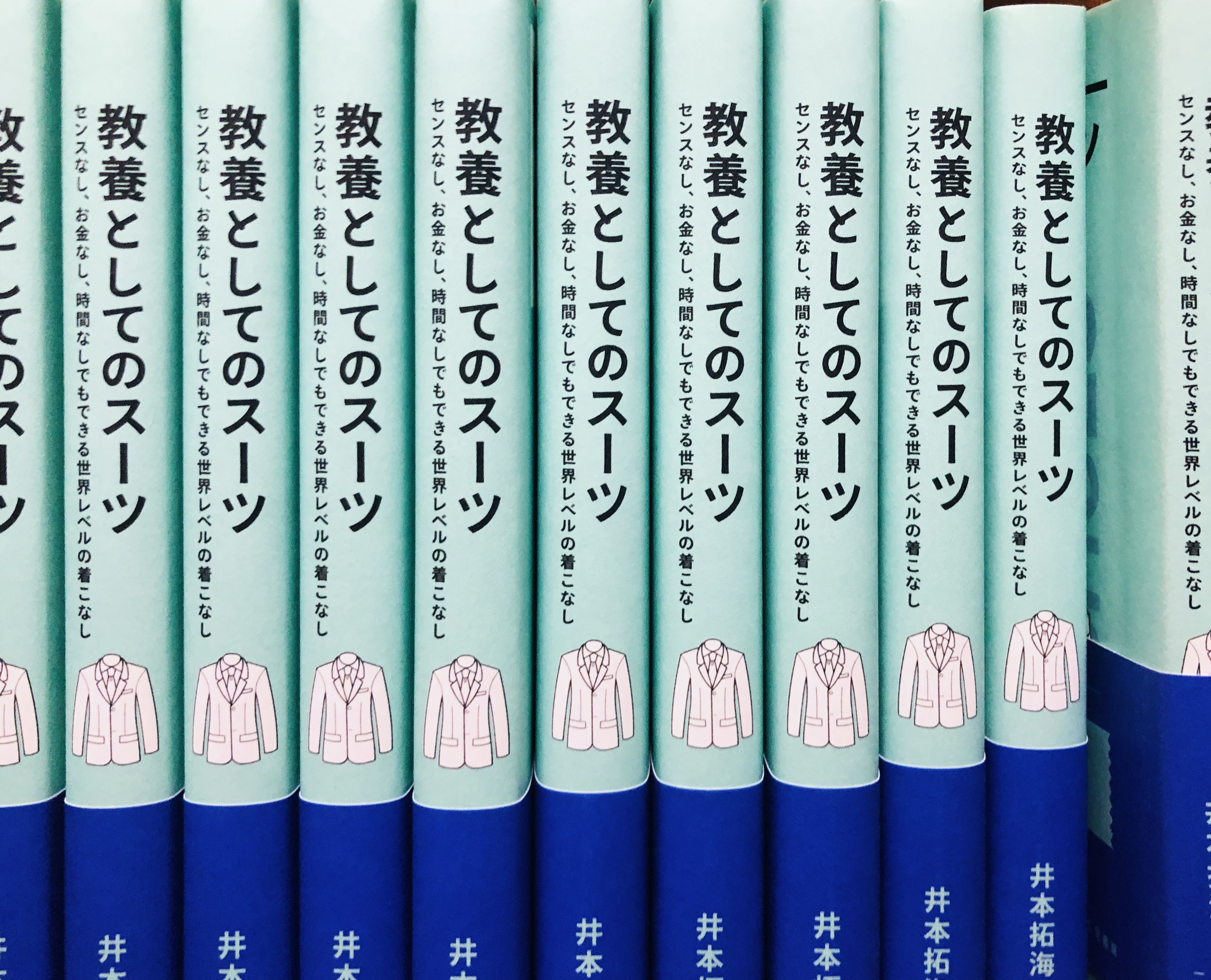








コメント